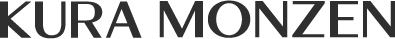Edo p. Figurine by Ninnami Dohachi, Tanuki dressed as Priest
Edo p. Figurine by Ninnami Dohachi, Tanuki dressed as Priest
Item Code: K692
受取状況を読み込めませんでした
京都の仁阿弥道八による 僧侶の衣装を着たいたずら好きな狸の美しい彫刻です。19世紀に作られたもので、両手を重ねて瞑想のポーズをとっています。底に署名があり、サイズは 24 x 24 x 27 cmです。右顎の下と尾に焼き割れがありますが それ以外は良好な状態です。 経年変化した木製の展示用ボックスに収められています。
道八窯は 亀山藩士の初代 高橋道八が1760年頃に粟田口に開いた窯で、道八の名は二代目当主によって陶磁器界の第一線に躍り出ました。皇室の崇拝も得て、江戸時代後期の京都を代表する陶工の一人に成長しました。仁阿弥道八(1783-1855)は初代 高橋道八の次男として生まれました。兄の早逝に伴い家名を継ぎ、1814年に京都五条坂(清水寺のふもと)に窯を開きました。古くから日本で高く評価されてきた中国や朝鮮の古代の型を研究・完成させたことで知られ、同時に茶道界での家の名声を高めることにも尽力しました。同時代の青木木米や永楽保全と共に、乾山や仁清焼だけでなく磁器の名手としても有名になりました。その後数十年にわたり、仁阿弥は高松、薩摩、紀州などの地方に呼ばれ、大名家や徳川家、西本願寺の窯の相談や設立に携わりました。仁阿弥代道八とその息子(後の三代道八)は1832年に地元の領主 松平氏に招かれ、四国の讃岐国にある讃窯で陶器を製作しました。彼はその後、1852年に息子と弟子の舅舅平を連れて再び日本に帰国しました。 三代目(1811-1879)は父の跡を継ぎ、最高水準の煎茶器やその他の磁器を数多く製作し、明治時代まで京都陶磁器の歴史に名を残しました。
三代目 高橋道八は「華中亭道八」の称号を使い始め、仁和寺宮から「宝橋」の称号を授けられました。晩年は祖父の窯に隠居し、息子で同じく華中亭を名乗った四代目 道八(1845-1897)に窯を譲りました。5代目(1869-1914)は1897年に養子となり窯元を継ぎ、当時トップクラスの陶工として活躍し、高弟の伊東陶山をはじめ後世に大きな影響を与えました。現在、窯は9代目が引き継いでいます。道八工房の重要性は、1870年代にヴィクトリア&アルバート博物館(ロンドン)が「最古の時代から現代までの磁器と陶器の歴史的コレクションを作り、芸術の歴史を完全に伝えるように構成する」という命令を受けて購入した一対の花瓶によって決定づけられるでしょう。2014年にサントリー美術館でこの作家を中心にした展覧会が開催され、ボストン美術館や京都国立博物館など、数多くの美術館でも彼の作品が展示されています。
タヌキは日本の民間伝承において重要な存在であり、そのいたずら好き、姿を変える能力、そしてユーモラスな行動で有名です。遊び好きで、時には道徳的に曖昧な性質で知られ しばしば変身と変装の達人として描かれ、欺瞞、順応性、そしてユーモアというテーマを体現しています。民話の中には タヌキが仏教の尼僧や僧侶に変装するものもあり、ユーモラスまたは皮肉な含みがあることが多いです。このイメージは神聖なものと不条理なものを融合させ、タヌキの生意気な性質を際立たせています。宗教的な人物に変装することは、精神的または厳粛な状況でも人を欺くタヌキの能力を強調しています。これらの物語は、たとえ神聖な場所であっても 騙されやすさと識別力の必要性について警告する物語です。ぶんぶく茶釜のような物語では、タヌキが僧侶や神聖な物(茶釜)に変身して人間を騙します。宗教的な人物に扮したタヌキは、偽善や外見への過度の敬意に対する微妙な批判として解釈でき、日本の物語のより深いユーモアを反映しています。
Share