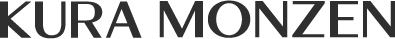江戸初期 p. 志野織部紅楼
江戸初期 p. 志野織部紅楼
Item Code: K411
受取状況を読み込めませんでした
17世紀/江戸時代初期の、鳳凰と花の文様が彫られハート型の蓋が付いた志野織部香炉です。本体の上部には 花のつるが垂れ下がったひょうたんの形に伸び、その下には膨らんだ足の上に香炉が載っています。直径10cm、高さ13cmで 全体的に非常に良好な状態です。現代の木製のコレクター用収納ボックスに収められています。
志野焼は、16 世紀後半の桃山時代(1573~1600 年)に生まれた 日本で最も尊敬されている伝統的な陶磁器様式の1つです。独特の釉薬と素朴な美しさで知られる志野焼は 特に茶道の文脈において、日本の芸術と文化において特別な位置を占めています。桃山時代に陶磁器生産の重要な中心地であった美濃地方(現在の岐阜県)で発展しました。当時としては大きな革新であった白い長石質の釉薬を使用した日本で最初の様式の一つであると考えられています。初期の志野焼は中国の陶磁器に触発されましたが、控えめで有機的な美しさを持つ日本独自の形に進化しました。志野では通常、鉄分を多く含んだ粗い粘土である美濃土が使われ、それが土っぽい外観につながっています。志野焼の特徴は長石から作られた白い釉薬です。焼成条件や釉薬の厚さの変動により、乳白色からオレンジ、赤、灰色まで、豊かな質感と微妙な色の変化が生まれます。陶工は鉄分を多く含んだ泥や釉下絵を用いて、植物、草、抽象的なモチーフなどの簡単な筆遣いで志野の作品を装飾することがよくあります。志野は、茶人たちがその素朴な優雅さを高く評価した桃山時代に最盛期を迎えました。織部や柿右衛門などの他の陶芸様式が人気を博した為、江戸時代初期(1603-1868)に志野様式は衰退しました。荒川豊蔵(1894-1985)などの先駆的な陶工たちの努力により、20世紀に志野焼は復活を遂げました。彼は古代の技法を再発見し、その復興に貢献し、人間国宝の称号を獲得しました。
共有