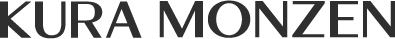アンティークな日本の木彫り、霊芝キノコの房
アンティークな日本の木彫り、霊芝キノコの房
Item Code: K212
受取状況を読み込めませんでした
中央に長い霊芝の束を束ねた木彫りです。19世紀後半から20世紀初頭にかけて作られたものです。長さは28cmで、状態は良好です。これは如意でしょうか、指根付でしょうか、それともパイプ入れでしょうか...?キノコの根元の後ろのスロットはパイプケースを示しているようですが、反対側の端にはパイプの小さい方の端を保持するものは何もありません。通常の根付は長い紐を帯に通して付けるのに対し、指根付は紐が非常に短く、根付自体を帯と着物の間に差し込むため、形は長く平らです。
霊芝は、2,000年以上もの間崇拝されてきた古代の「不老不死のキノコ」です。西暦1世紀の班固の詩には、霊芝に捧げられた頌歌があります。道教寺院は「キノコの住処」と呼ばれ、その神秘的な教えによれば 霊芝の濃縮煎じ薬を使用すると、信者は天上の「キノコ畑」に住む仙人の魔法のエネルギーを受け取ることで霊を見たり、霊になったりできるとされていました。西暦3世紀の『神農薬経』では、智を6つのカテゴリに分類しており それぞれが体の様々な部分の気、つまり「生命力」に効果があると考えられています。
如意(中国語では如意)は、仏教や道教の芸術や文化的資料で使用され、見られる儀式用の笏またはお守りです。インドの仏教僧が使用したサンスクリット語の「儀式用の笏」であるアヌルッダに由来すると思われます。後にこの概念が中国に持ち込まれ、権威の象徴となりました。そこで如意は背中の掻き棒と融合しましたが、その背後には興味深い物語があります。仏教僧は結婚することがなかったので、子供を持つことを諦めました。背中の掻き棒(孫の手)は文字通り「孫の手」と翻訳されます。僧侶には孫がいないため、背中を掻いたり老後の世話をしてくれる人がいないため、生まれなかった人々の霊が笏に具現化されます。笏は僧侶にとって最も貴重な物の一つです。如意は社交の場で持つ文人や貴族にもよく見られ、その本来の機能は、ハエたたきや扇子と同様に、持ち主が「議席につく」資格を与える笏であったことは疑いようがないです。芸術では、如意は仏教の聖者や道教の仙人の象徴としてよく登場します。中国の如意は、ヒスイや貴金属などの貴重な素材で作られていたり、宝石がちりばめられていたりすることが多いですが、質素さと控えめさを強調する日本では木や竹で作られたシンプルで飾り気のない自然物の美学が重視されています。
共有