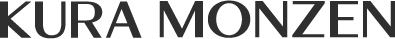古代木製天狗面、鎌倉時代から室町時代
古代木製天狗面、鎌倉時代から室町時代
Item Code: K855
受取状況を読み込めませんでした
鎌倉時代から室町時代にかけて制作された烏天狗の鬼面です。赤と黒の多彩色で覆われた木彫りで、奇抜な顔立ちと巻き毛が描かれています。鳥のような嘴を持つ天狗のこの面は、眉を寄せ目を大きく突き出し鼻は大きく、12世紀から14世紀にかけて制作されました。背面のノミ跡を含む全体的な彫刻様式と色彩は、この年代と一致しており、下を向き瞳孔が密集している点は、この初期の時代の特徴です。面の寸法は21.5 x 14.5 x 8 cmで、破損していたため顔の左側に再接着されています。古い桐箱に入っています。
日本における仮面芸術は豊かな儀式や演劇の伝統と切り離すことのできないものであり、古代から桃山時代に能楽が体系化されるまで脈々と受け継がれてきました。日本の仮面は単なる装飾品ではなく、精神的、社会的、そしてパフォーミングな機能を体現し、人間界と超自然界をつなぐ媒介として、また共同体的な表現の手段として機能してきました。
現存する最古の仮面芸能は、飛鳥時代と奈良時代に大陸から伝来した祇楽(7~8世紀)です。寺院や宮廷の儀式で演じられたこの行列舞踊は、ほとんどが無音で高度に様式化されており、仮面は外国の使節、勇ましい守護者、動物、滑稽な人物などを表現していました。祇楽の仮面は記念碑的なスケールと誇張された容貌が印象的で、日本の芸能における中心的な媒体として木彫りの仮面が用いられる先例となりました。この伝統は平安時代に衰退しましたが、その形式的な語彙と彫刻的な感性は、後の仮面芸術に影響を与えました。
平安時代以降に栄えた舞楽は、祇楽の優美な対極に位置します。宮廷や主要な神社で演じられた舞楽は、中国や朝鮮の舞楽をモデルにしつつ、本独自の美意識を育みました。武者、神々、龍、そして外国の高官を描いた舞楽の仮面は、威厳と儀式の厳粛さを表現するためにデザインされ、舞楽において仮面は単なる舞台装置としてだけでなく、貴族の儀礼文化の象徴として機能し、所作、衣装、そして物語を視覚的に統一しました。
宮廷の仮面に加え、仮面は農耕や宗教儀礼においても重要な役割を果たしました。平安時代に田園で豊穣を祈願する踊りとして始まった田楽は、徐々に都市や寺院にも浸透していきました。田楽の仮面は比較的簡素で、村人や滑稽な人物、そして時には神々を象り、即興性と共同体的な性格を反映していました。同様に、行道と呼ばれる儀式行列においても、仮面は仏教的な宇宙観を表現するために用いられました。仁王、菩薩、その他の守護神は、精神的な物語を劇的に表現し、神聖な存在を呼び起こすために、特に寺院の行列や奉納式において着用されました。
鬼を追い払う儀式的な慣習は、平安時代に始まり中世まで続いた、正月や節分の日に行われる追儺に代表されます。参加者(多くの場合、儀礼の専門家)は、邪悪を祓い、空間を浄化するために、奇怪な鬼の面をかぶり、人間と鬼の力との象徴的な闘いを演じました。これらの面は、唸り声を上げる口、突き出た目、突き出た角など、誇張された形をしており、そのパフォーマンスは、守護の儀式であると同時に、集団の見せ物でもありました。追儺は、鬼に豆を投げるといった後の民俗習慣に直接影響を与え、面、儀礼、そして社会慣習のつながりを保っています。
鎌倉時代から室町時代にかけて、これらの要素は能楽の発展へと収束しました。舞楽の形式的な優美さ、行道の精神的な重み、そして田楽と追儺の滑稽でグロテスクな生命力に着目し、能は人間、神、そして鬼の役柄を演じる様々な仮面を体系化しました。室町時代の「しかみ」や「小べしみ」といった仮面は、激しい感情や超自然的な状態を体現し、桃山時代の洗練は、儀式と劇の両方の場面で用いられる天狗などの鬼面を含む、安定した表現様式を生み出しました。線と形に細心の注意を払って彫られたこれらの仮面は、演劇の伝統の宝庫となり、何世紀にもわたる精神的および芸能的知識を守り続けています。
共有